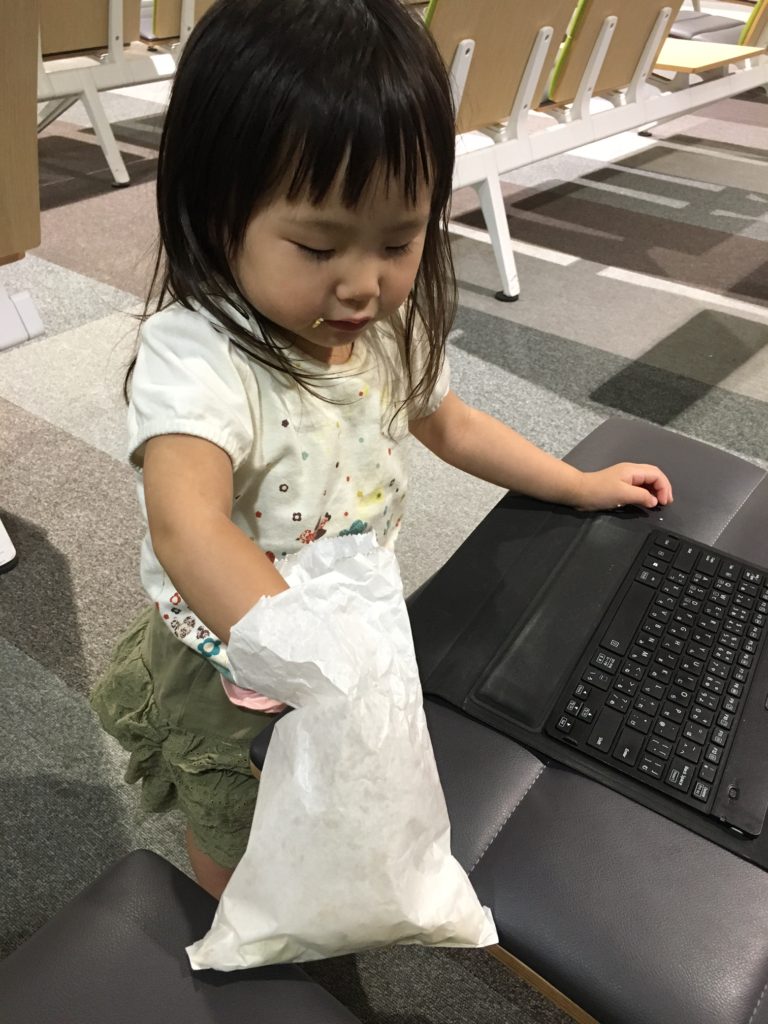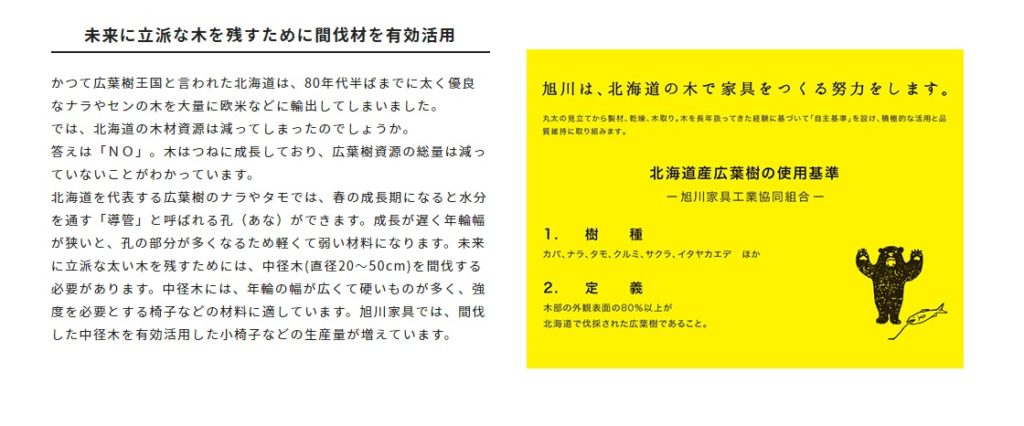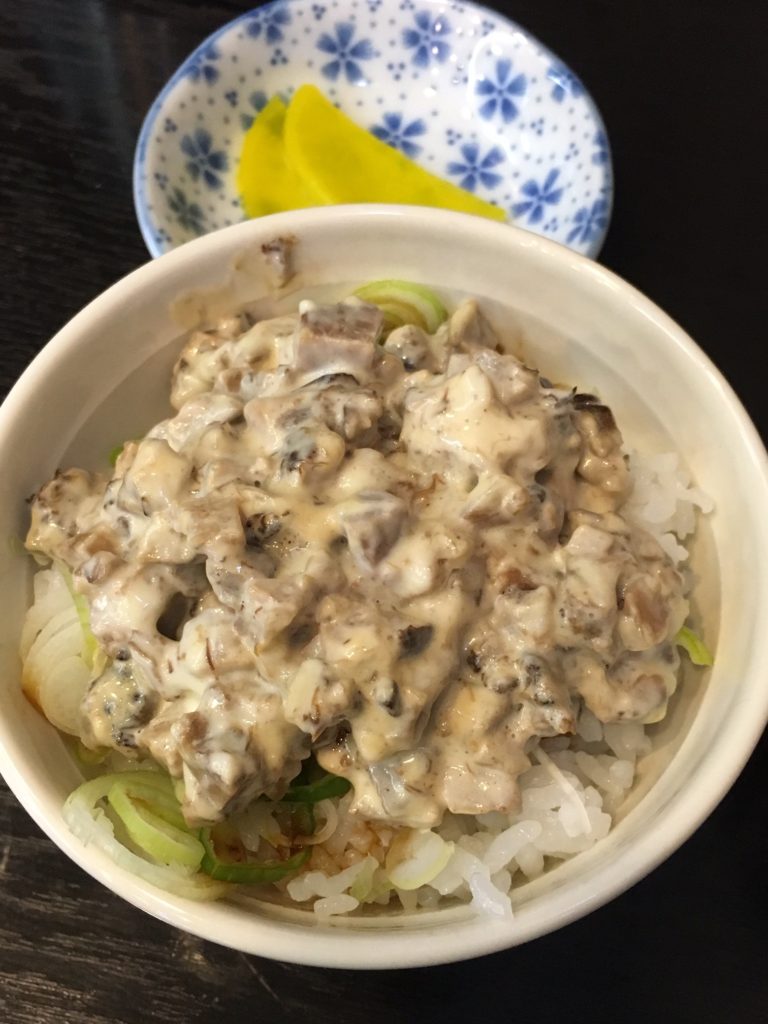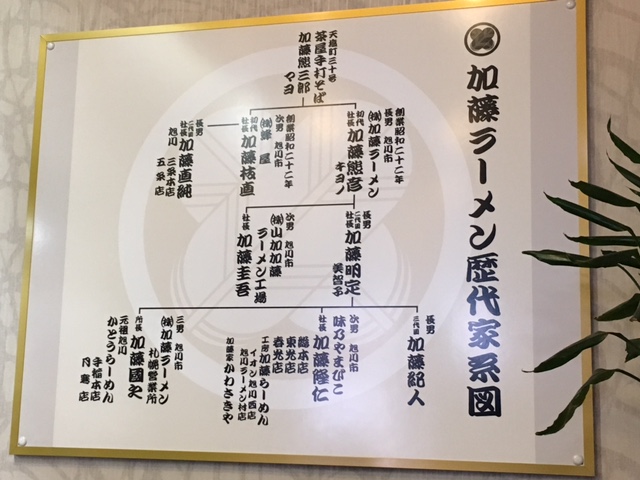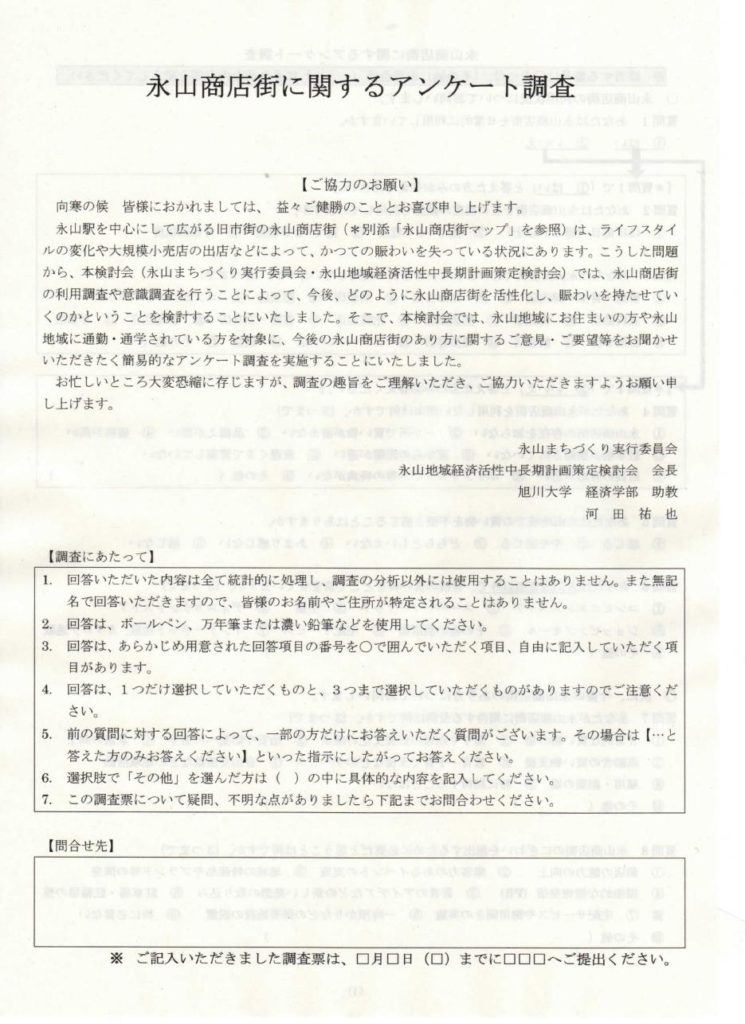地権者さんの側と相談中の土地の問題は、なんとなく良い方向に進んでる感じがする。なのでそれを前提に、総事業費を洗い直している。でもいろいろ考えてると、頭の中がお花畑になってきまして。

おっきなところだと、土地は三筆で560~600万円ほど、住宅は1100~1500万円ほど、小屋は400万円以上・・・。ほかに謝礼のたぐい、申請費用、各種工事、井戸掘削、自転車、暖房関係、宣伝・広告・・・。3カ月はまったくお客さんが来なくても食っていけるようにしないといけないし。
最初にソロバンをはじいたのが五月の半ばだったような気がするけど、その時はなんやかんやで、2100万円くらいが総事業費のイメージだった。当時は土地は1筆。でも現実的にいろいろ詰めていくと、そんなんじゃ無理で、冬を生き抜くには計画性のある暖房システムが欠かせない。長い目で見たら、エネルギーとカネの地域内循環について手を抜くことはできない。
「借りれるだけ借りて、キャッシュを残しときなよ」「初期投資は過剰にならないように」「最初の集客が命。そこを削るなよ」・・・。ありがたいことに、いろんなアドバイスをいただく。いっぺんに何もかもできないとは思うけど、一方で走り始めこそが肝心だとも。
う~ん。逆立ちしても、酒絶ちしても、お金が足りない。使えるお金を集めるにはどうするのか。
①地元金融機関からの融資額を増やす
②政策金融公庫にもお願いする(そのつもりではいたけど)
③クラウドファンディングを頑張る
④フェアレディZに続いてファミリーカーを売る
⑤施設・設備を妥協する
うーん。。。確かにいろんな方法があるけど、本質的じゃないような気も。「持続可能な暮らし」とかカッコよさげな事をうそぶいているけど、そもそも事業として持続可能なのか。
売り上げや、本当の粗利がこんだけ見込める→だからこれだけ投資できる、という考え方が必要なのでは?
たとえ土地がうまくいっても、壁は絶え間なく立ちはだかりそう。まだまだスタート地点にも立てていない。