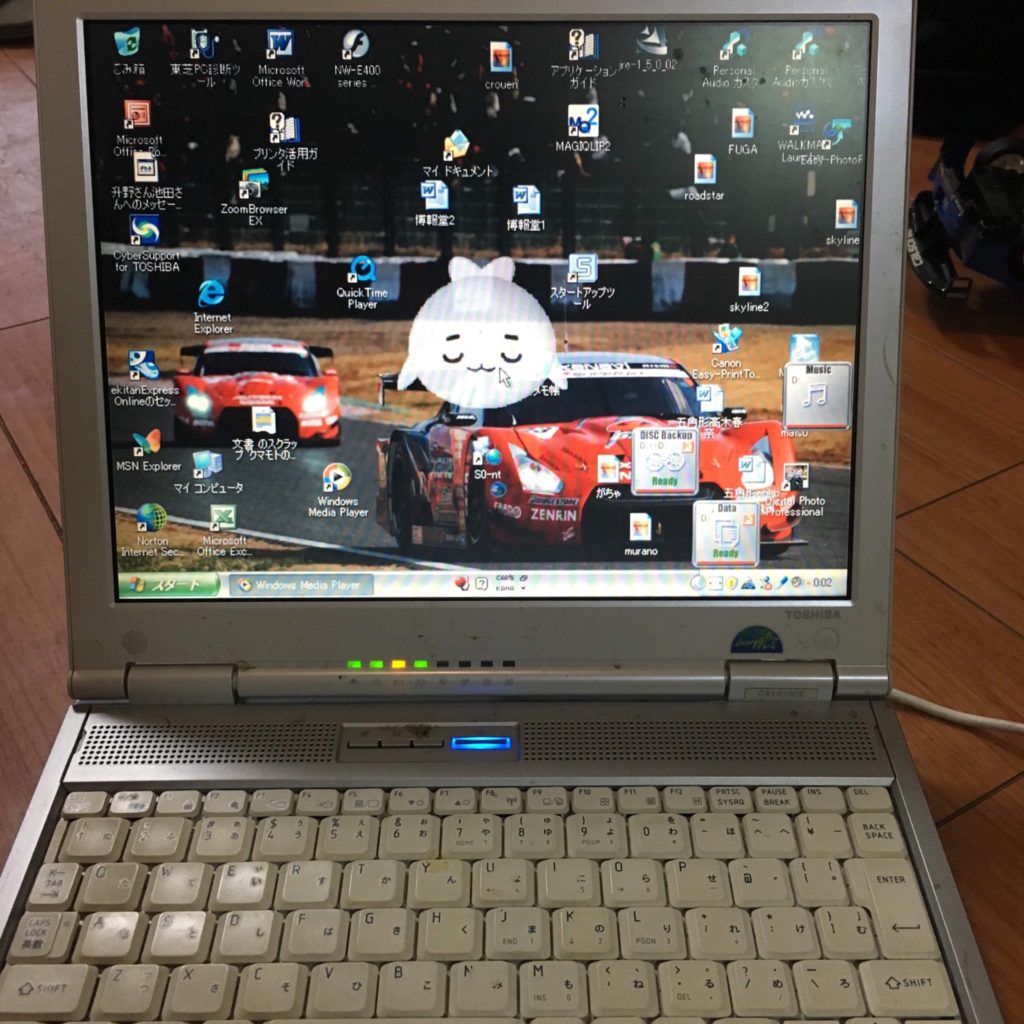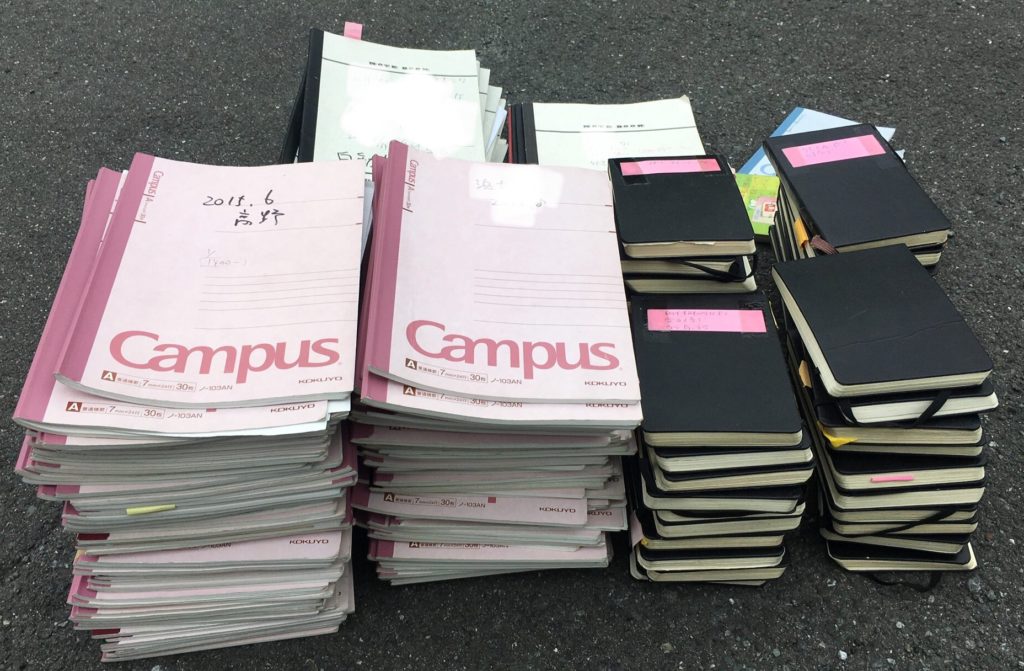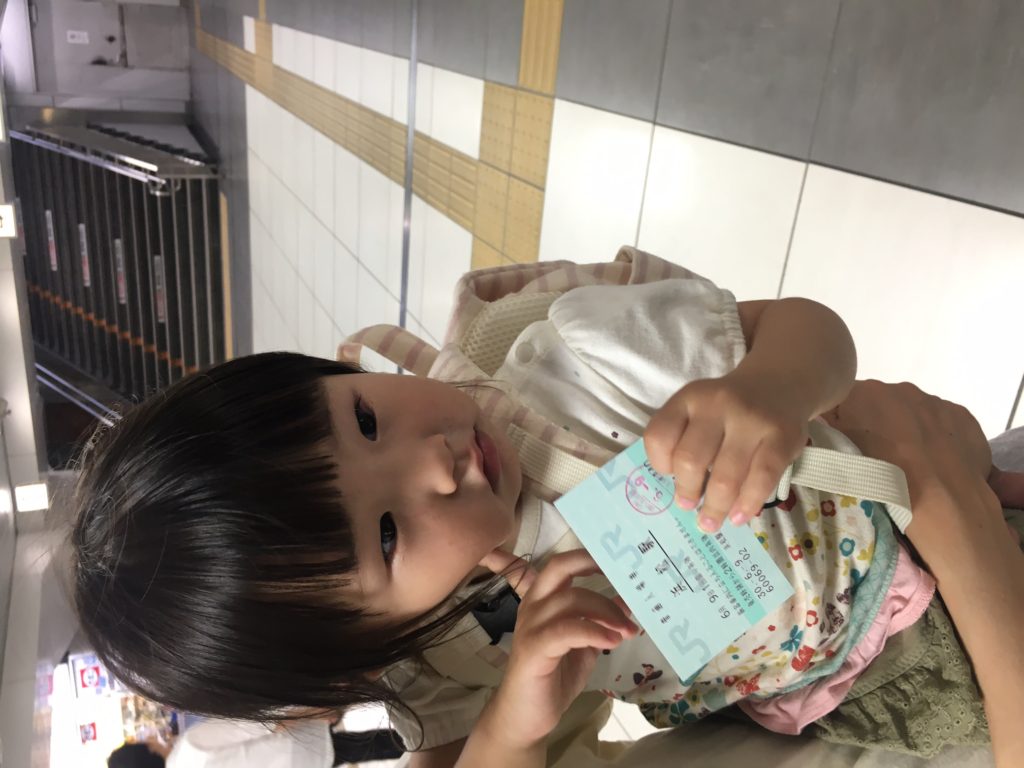せっかく大学を出て入った会社、しかも大きく安定した会社を辞めて、素人が得体の知れない事業を始めると言ったら、親族なんかからはたいてい、こんな反応がある。「子どもが3人いて、育てられるの? ごはん食べていけるの?」「失敗すると思うけど」
そりゃそうだ。
親になってみて思うのは、まず心配することが親の仕事みたいなもんだし、リスクを飲み込んで子どもを信頼し、「本人が決めたことだから」と黙って応援するのなんて、めちゃくちゃ胆力がいる。そもそも自分のこれまでの経験の範囲でしか、良し悪しも見通しも判断できないだろうし、経験を超えた未知のことを目の前にすると、普通は思考停止になっちゃうだろうなと思う。
5年前に結婚した時、自分の父方からは猛反対に遭って、事実上の縁切りだった。
「死ぬまで会いたくない」と言われて実際に葬式まで会えなかった祖母もいて、かなりきつかった。でも今なら「みんな幸せにやってるよ」と胸を張れるし、その状態をキープしていかなきゃと、気が引き締まる。原動力になる。祖母も意地悪したくて言ったわけじゃないし、それぞれの考え方でかわいい孫を心配してのこと。
一方で驚いたのは、母方の祖父が、血のつながっていない今の長男(大滋)を最初に紹介した時からかわいがってくれ、「浩司(わたし)が大滋を自分の子だと言うなら、俺らのひ孫だ」と受け入れてくれたこと。妻(茜)に対しても「浩司がいい人と思うなら、そりゃいいんだろう」という風だった。母方の祖母もそんな感じ。
これにはやられた。反射的に尊敬し、誇らしくなった。
めちゃくちゃ心強かったし、「こんな風に子どもや孫を認められるような、愛情深い親になりたい」と激しく誓った。そう言ってくれたから、なんとかやってこれた。
認めてくれる人が少数でもいるなら、もっと他の人にも認めれるように結果を出すまでだなと。
はじめから理解されなくても、プロセスと結果を見せることで、ちょっとずつ理解を広げていく方法はアリだと思う。もちろんいろんなハレーションや、失うものもあるけど、賛成ばかりというのは誰でも思い付くことで面白くもないし。
いま愛情深い親になったかどうかはおいといて、子どもにどんな事を伝えていくべきなのか、っていうのは、それなりに考えてきたつもりではいる。
小学校の予備校みたいな教育は幼稚園に求めないし、画一的な設備に囲まれた園庭よりも自然に囲まれて遊んでほしいし、(本人たちが望めば別だけど)絶対に受験戦争で戦わせたいとは思わないし、「みんなが行くからとりあえず大学」に違和感を持ってほしい。アタマより五感を発達させて、きれいなもの、本物にたくさん触れてほしい。反面教師にしてほしい、というのもあるけれど。
「ここでは足りないな」「違うな」と自分で思うなら東京や海外に行けばいい。親の希望なんて聞こうとしなくていい。親は時には歯を食いしばって我慢し、認めて受け入れ、後ろからそっと手を添えるくらいが丁度いいのかな、というのが今の気分。というか究極の理想。
「新しい仕事と暮らしをはじめて、大学に行かせられるくらい稼げるのかしら」と思ったこともあるけど、奨学金もあるし、最低限の備えがあれば、なんとかなるはず。甘いと言われるかもしれないけど、そう思うんだから仕方ない。大病にかからず、働ける体なら、必死に働くことはできる。
あした死ぬかもしれないし、世の中はどんどん複雑に不透明になってくる。人間は自然だけじゃなく、人工知能にも向き合って共生しつつ、「人間」を見つめ直さないといけない。
確かなことなんて何もないんだから、自分で考えて自分でリスクを取って楽しめる人になってほしい。親としてはお金よりも、そんな環境や雰囲気をつくりだしたいし、親のやっていることを見てほしい(失敗したらごめん)。
新天地でその一歩を踏み出せるかどうか。そんなドキドキの場所に、いまわが家はいる。