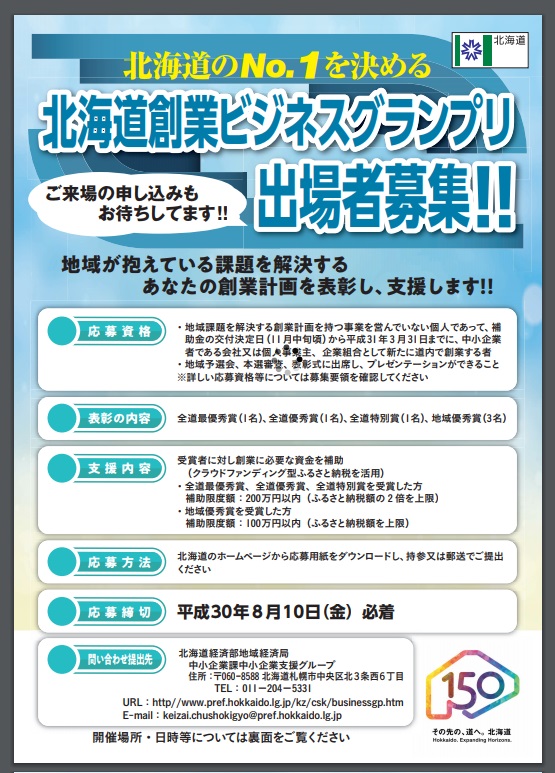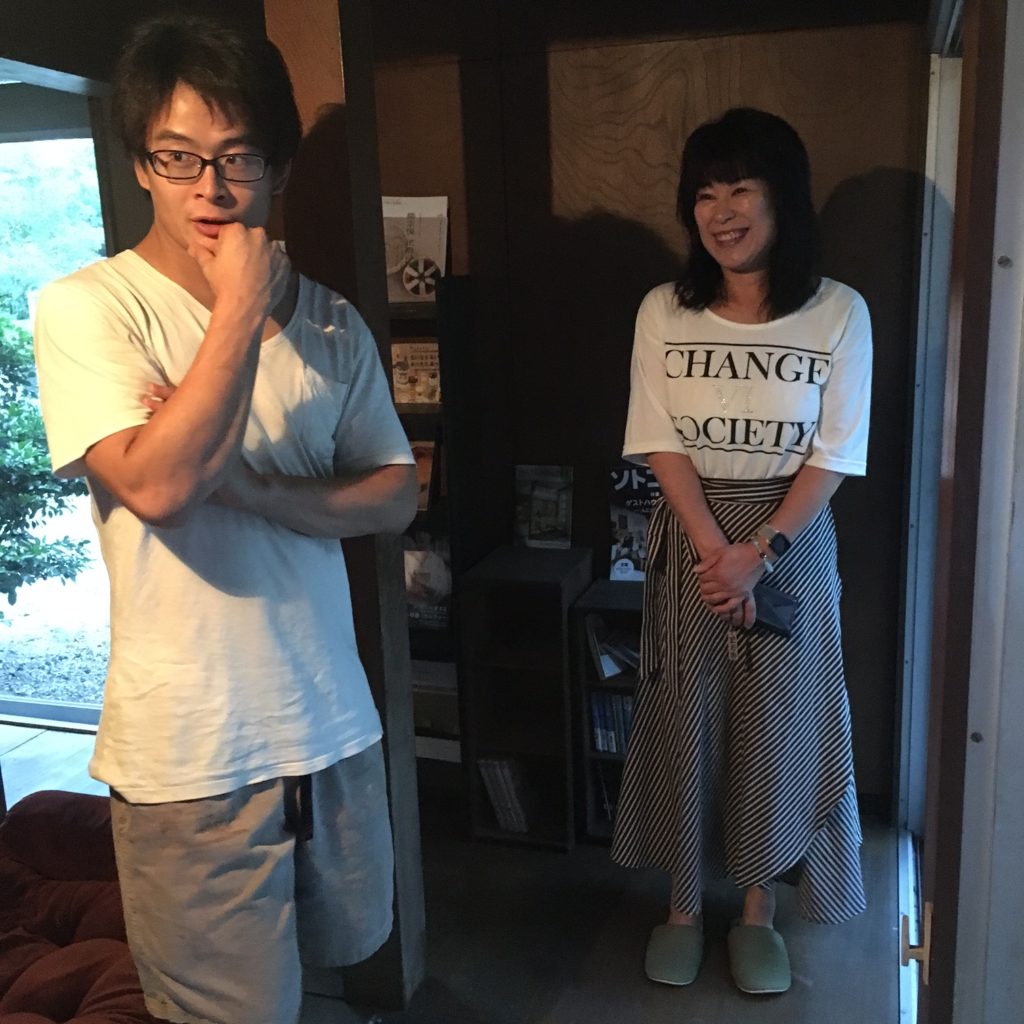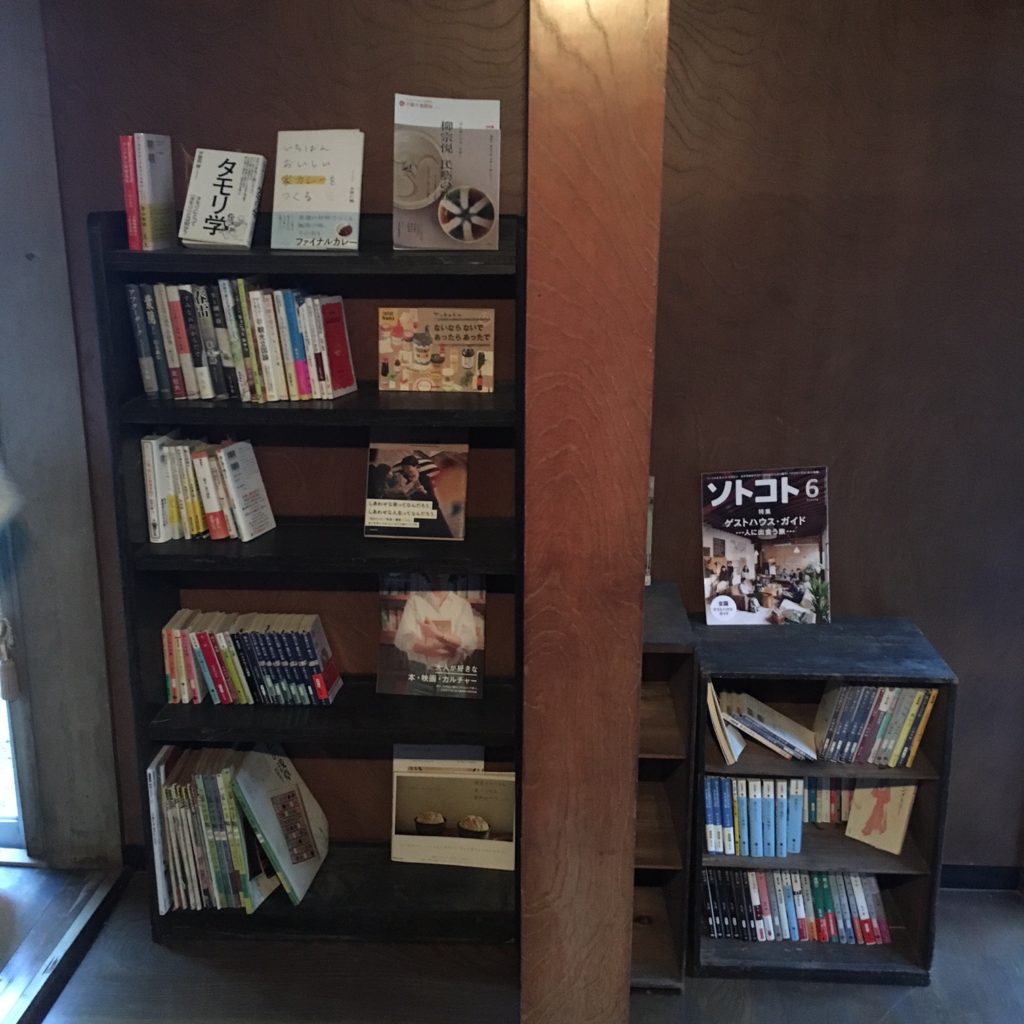5日近くブログ更新が滞ってしまい自己嫌悪。ちゃんと習慣をつけないかんのでプレッシャーかけるのは大事だけど、苦痛になってはいけないので、めげずにいこう。うん。
8月18日(土)は掛川駅前の軽トラ市に行って「麹のミルク割り」を買って、近くの製茶会社がやってる「きみくら」で翌日からの旭川行きのお土産を購入。きみくらはしょっちゅう行って新鮮さがないので、ほぼ隣にある「ラーメンショップ」に初チャレンジ。「塩コリコリのり」みたいな一風変わったのを頼んだけど、岩のりが入っていたのは確認できたものの、なにがコリコリなのか分からずじまい。商品説明を見ても書いてなかったので、消化不良感。味は、、、うん。

掛川をお暇して、いつもは浜松方面に帰るところだけど、今日はやる気を出して熱海に向かった。150キロくらいあるんだよね。でもいかなきゃならぬ理由がこれあり。
ちょうどこの前の日、毎日新聞にこんな記事が出ていて。

公園ゲストハウスをつくる人間としては、見ないわけにはいかないと。18日までの3日間限定だし、ちょっとでも早く「熱海の奇跡」を見てみたかったし。
ひたすら東名高速を走って、沼津インターから下道を走りまくり、けっこうな峠を越えて、熱海の温泉街たどり着いた。
まず人の多さにびっくり。「昔はよかったけど、いまは寂れすぎて・・・」というのがかつての熱海イメージだったけど、老若男女、とくに若い人が商店街をゾロゾロ歩いてる! 歩道が狭いし、よけいに活気を感じさせる。お店がいっぱいあって、色彩がほんとうに豊かな感じで。あー、いいスパイラルが、なんかおもしろそうなことをやるぞ!っていう空気が流れてるんだなー。あー、昔の温泉街ってこんな風に賑わっていたのかなーと想像してしまった。

今や有名になった「熱海プリン」は外までレジ待ちのお客さんがいるし、干物屋さんもなんだか楽しげで、ふらりと入りたくなる。そしてその向かいには、


いまや全国的な有名ゲストハウスだけど、めっちゃまちに開かれている。干物とビールを売っていて、なんかすごい羨ましい空気感。日本じゃないみたいな、いい時間が流れてた。飲めるスタンドもある。泊まれなくても楽しめるけど、「泊まると熱海がくせになる」のキャッチコピー通りだわ。
毎日新聞の記事に出てた公園は、MARUYAさんのお隣だった。向かいのお店で売っているアイスが食べられる「モバイルキヨスク」、ベンチ、子ども用のトンネル。歩く人がたくさんいるので、こういう空間って貴重だわ。




ほっこりして写真撮ったりしてると、この公園で、「熱海の奇跡」の著者で熱海再生の仕掛け人、市来広一郎さんを発見! 生で拝見できるなんて、なんと運命的な!と勝手に思い込み、「市来さんですか?」と声かけを決行。気さくにお話ししてくだり、旭川でゲストハウスをつくることもお伝えしてしまった。
熱海には15分しかいられなかったけど、ほんと来てよかったー。どうしようか悩んだら行動あるのみ。
夜は三重県から会社の先輩・後輩が浜松に駆けつけてくれ、たのしい宴。いまは立場も勤務地もいろいろ、考えもいろいろだけど、かつて同じグループでけっこうなエネルギーを注いで取材をしていた間柄。こうしてまた集まってもらえるのって不思議な感じがするけど、とにかく落ち着く。一緒に乗り越えてきたことを思い出して、パワーがでた。今の会社にいたからこそ今の価値観ができたわけで、皆さんとのご縁に感謝するほかない。

別れ際。「がんばって」と握手を交わした、その力の強さを忘れないでいよう。