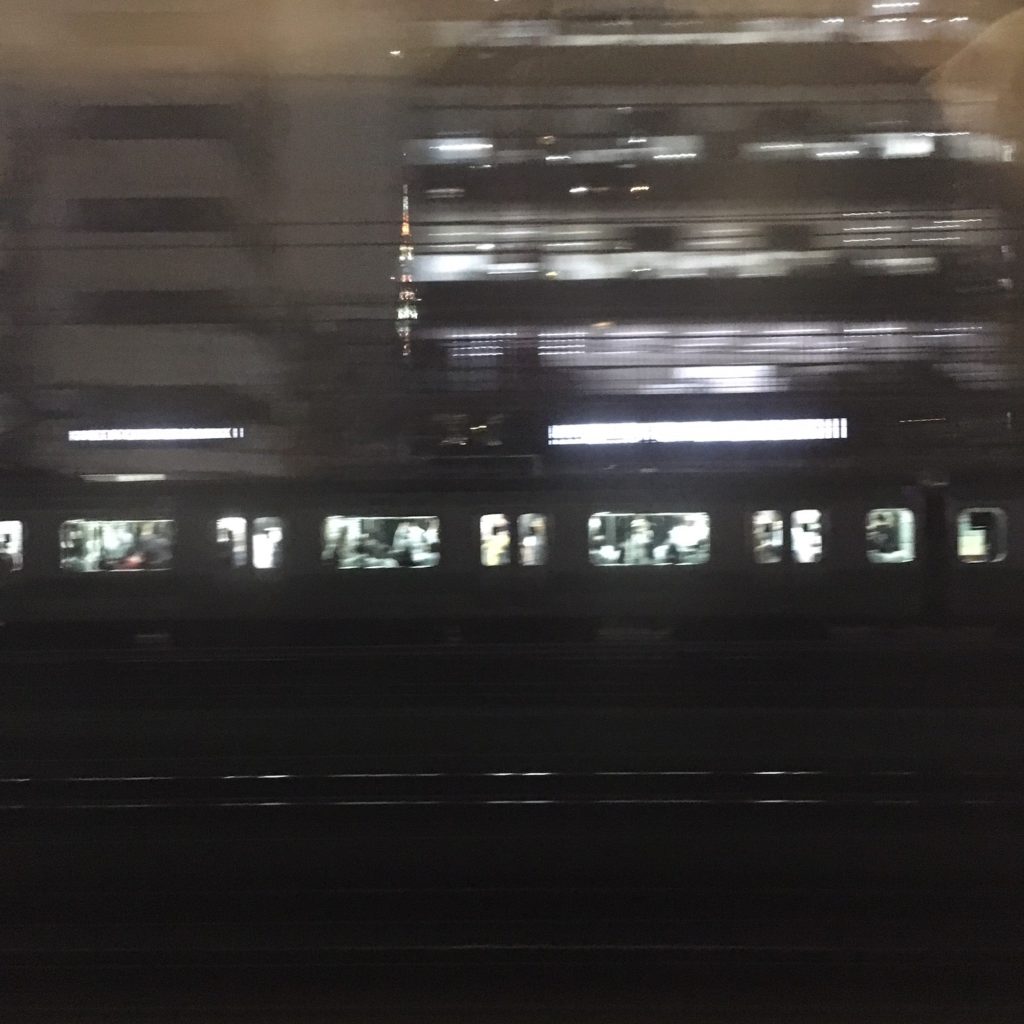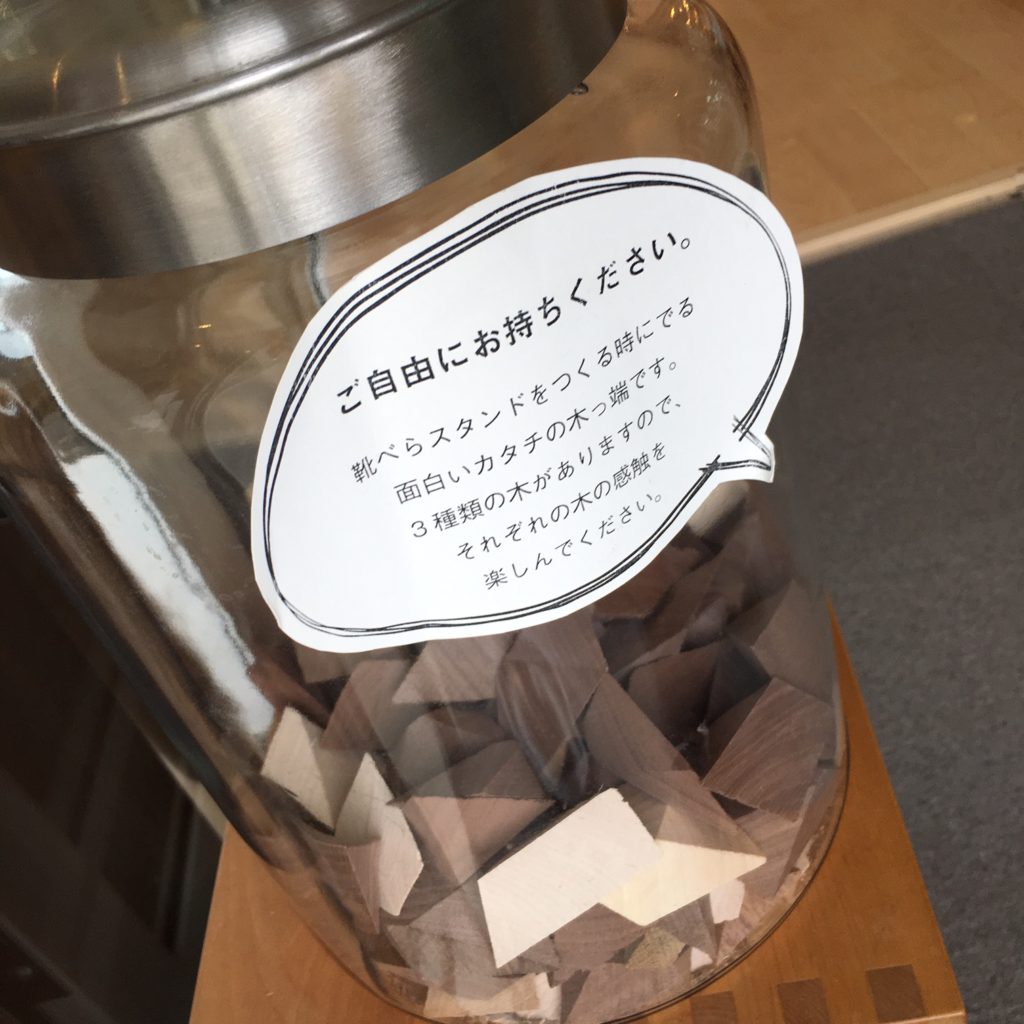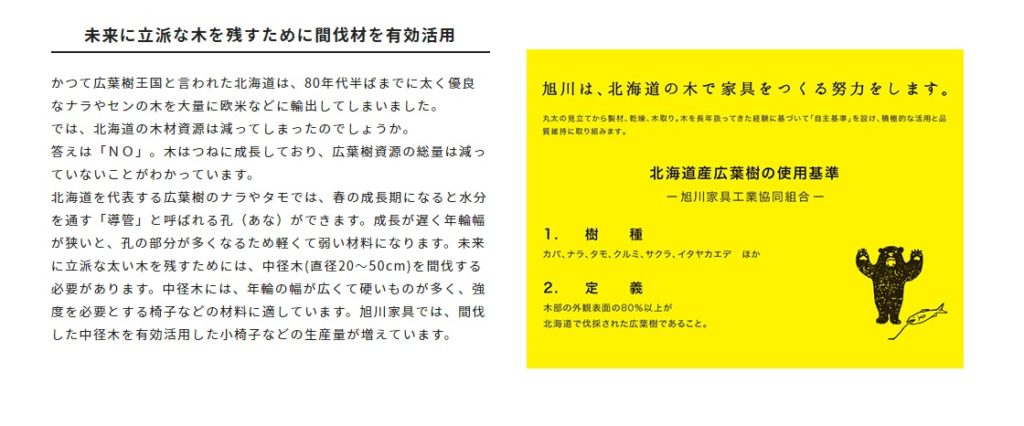ドトールできんきんに体を冷やした後は、夜の待ち合わせまで時間があったので、表参道・青山に向かうことにした。
ぶらぶらしたり服を買いたいわけではなく、旭川が世界に誇る家具メーカー「カンディハウス」の東京ショップに行きたかったのです。
ひっさしぶりに表参道交差点に出て、コムデギャルソンの方面に歩く。それっぽい感じのオネエサン、オニイサン、メルセデスやアウディ、アルファードなんかが道を支配している。完全に旭川とは空気が違っているー。浜松とも。
奇異な建物が目を引くプラダのある交差点を、表参道ヒルズから見て右手に曲がり、ぐんぐん行くと、わがゲストハウスの総事業費のたぶん3倍は行くであろう超高級(そう)なマンションがあり、その向かいに東京ショップはあった。

佇まいも、明らかに旭川ショップとは違う! そして確実に入りにくい(笑)脂汗がでてきていったん通り過ぎるも、「これを避けては成功はない」と自分に言い聞かせて、シャツがズボンの中に収まっているか確認して、深呼吸して、この異世界へ足を踏み入れることにしたのです。
エントランス近くで最初に目にしたテーブルに、どこかで見た黄色いシールが。そう、道産材をもっと使ってこーよ!っていう「ここの木の家具プロジェクト」です。うれしい。これを東京で見られるなんて。
ただ目を奪われたのはこのテーブルではなくて、そのそばにあった、木工品。

静岡県出身で北海道に移住し、森林が9割を占める下川町で創作されている「クラフト蒼」の臼田健二さんの作品。ナラやサクラとかを使って、ショップの人によると、生木をくり抜いて作っている。大きいものはサラダボウルになるし、小さいものはぐい呑みにしてもいいんだと。洗った後にちゃんと拭くなど、丁寧なケアが欠かせないのも、愛着が増すようでうれしくなる。迷わず購入。
ショップ内をグルグル見渡して、本気で欲しいものにもう一つ、出会った。下の写真のイージーチェア。

なんとこれ、座面と背面に馬の革を張っているのです! 知る人ぞ知る、日本で唯一の馬具メーカー「ソメスサドル」(砂川市)とのコラボレーションってこと。憧れのソメス! 新千歳空港にもショップを構えてるので目にする機会は少なくないけど、いろんなストーリーがあって、一度本社のファクトリー・ショールームに行きたいとずっと思ってる。
このチェアは38年前に商品化されたものを復刻させたとか。当時よりより丈夫な革を使ってるのだそう。勧められたので、厳かに腰を落としてみた。張りがあって厚くて固くて、でも座るほどに体になじむ。多分これは、無二の座り心地。ストイックではないけどシャキッとくつろげる、っていう新しい感じ。真剣に欲しいけど、34万円ときては数年単位で考えないと(笑)

店を後にする時は、店員さんやフロアに立たない社員さん?、搬入の方々?とかいろんな人にお見送りされて、気分はすっかり青山のオシャレ住民。「ソメスサドルさんは青山にお店ありますので、お時間ありましたら是非」とショップカードを渡された、家具と馬具、パートナーとして互いに高め合ってるんだなと感じて、ほっこりした。素敵。
夜は日本国の中枢を担う人物を日夜追っている、金沢時代にお世話になった超多忙な先輩記者とアメリカンなお店で乾杯。ご縁に感謝!